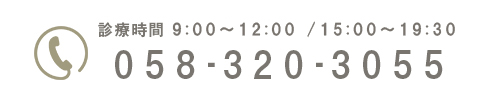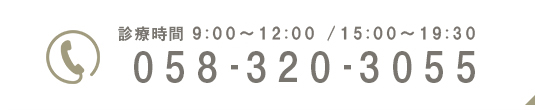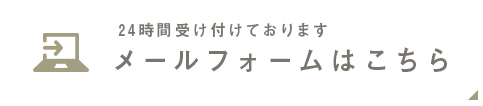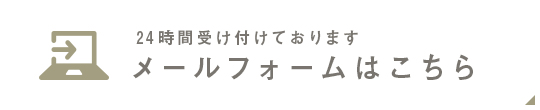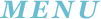遺伝するのは歯並びではなく「骨格」です
自分の歯並びが子どもにも影響するのでは?と不安に思う親御さんは少なくありません。特に、ご自身が矯正治療を受けた経験がある方であれば、お子さんの歯並びには一層敏感になることでしょう。
親子で歯並びが似ていることは珍しくありません。これは、顎の大きさや顔と顎のバランスなど、歯並びに影響を与える骨格の遺伝情報が子どもに受け継がれるため、結果的に親と似た歯並びになることがあるからです。
生まれ持った骨格を変えることは難しいものの、歯並びは後天的な要因によっても左右されるため、まずは歯並びに悪影響を及ぼすような癖や生活習慣がないかを確認することが、きれいな歯並びへの第一歩になります。
遺伝しやすい歯並びはある?
骨格が影響している歯並びは、すなわち遺伝の影響を受けやすい歯並びといえます。主に以下のような不正咬合は、骨格的要因が強く関係しています。
● 叢生(そうせい)
いわゆる乱ぐい歯や八重歯など、歯が不規則に並んでいる状態です。
顎の骨が小さく歯が並びきらないことが主な原因とされており、これは遺伝による骨格の影響が大きいと考えられます。
● 上顎前突(出っ歯)
上の歯が下の歯より大きく前に出ている噛み合わせのことです。
骨格に起因することが多く、遺伝的要素が強い歯並びです。
● 反対咬合(受け口)
下の歯が上の歯より前に出ている状態を指します。
こちらも骨格的な要因が大きく、場合によっては矯正治療のみでは改善が難しいケースもあります。
歯並びを悪化させる生活習慣
骨格の遺伝に加えて、家族共通の生活スタイルや癖も歯並びに影響を及ぼします。以下のような習慣には注意が必要です。
● 柔らかいものばかり食べる
柔らかい食事が中心になると咀嚼回数が減り、顎の筋肉が発達しません。結果的に顎が十分に成長できず、歯が並ぶスペースが足りなくなってしまいます。
● 指しゃぶり
幼児期によく見られる癖ですが、長期化すると前歯に常に圧がかかることで、出っ歯になる原因になります。
● 爪を噛む
固い爪を噛むことで歯に強い力がかかり、噛み合わせに影響が出ることがあります。
● 頬杖をつく
片側からの外力が歯列にかかると、噛み合わせや歯の傾きに影響を与えます。繰り返すうちにV字型の歯列になることも。
● 口呼吸
鼻炎やアレルギーなどにより口で呼吸する癖があると、下顎が下がり舌の位置も低くなります。これが顎や口周りの筋肉の発達を妨げ、出っ歯や受け口の原因になることがあります。
何気ない日常の癖や行動が歯並びに悪影響を及ぼすことがあるため、早い段階で生活習慣を見直すことが大切です。
アレルギー体質と歯並びの関係
アレルギー体質は遺伝しやすい傾向があります。
アレルギーが直接歯並びに影響することはないように思えますが、アレルギー性鼻炎による慢性的な鼻づまりが原因で口呼吸が習慣化してしまうと、前述のように歯並びに悪影響を及ぼすことがあります。
このように、一見無関係に思える体質や疾患も、歯並びと深く関係していることがあります。
まとめ:歯並びの7割は後天的な要因
歯並びには確かに遺伝的要素がありますが、その影響は約3割程度といわれています。
残りの7割は生活習慣や癖などの後天的な要因で左右されることがほとんどです。
「遺伝だから仕方ない」と諦める前に、日々の習慣を見直してみましょう。
適切な生活習慣と早期の予防意識を持つことが、お子さまの健やかな歯並びの維持につながります。