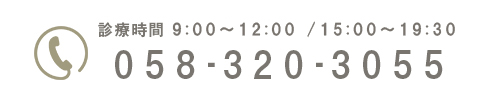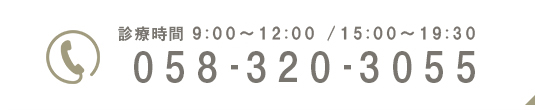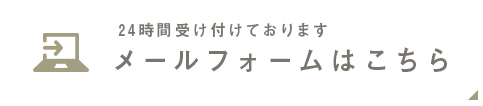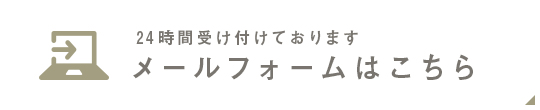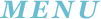1.歯を磨かない人・口腔内を清潔に保てない人
歯にプラーク(歯垢)が溜まり、口の中が細菌だらけの状態になると、間違いなく歯周病のリスクは高まります。歯周病は生活習慣病の一種であり、日々のセルフケアが何よりも重要です。歯みがきやお口のケアは、歯周病だけでなく虫歯の予防にも欠かせません。
2.たばこを吸う人
喫煙は歯周病にとって最大級のリスク要因とされており、喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病になりやすく、進行も早く、治療効果も出にくいことが分かっています。主な理由は以下の通りです。
歯ぐきの血行が悪化し、酸素や栄養が届きにくくなる
免疫機能が低下し、白血球の働きが弱くなる
唾液分泌が抑制され、プラークや歯石が付着しやすくなる
3.糖尿病の人
昔から糖尿病の人は歯周病になりやすいといわれています。高血糖状態になると唾液の分泌が減少し、口腔内が乾燥しやすくなります。乾燥することで白血球の働きが弱まり、歯周病菌が繁殖しやすくなります。糖尿病の方が口腔ケアを怠ると、歯周病を発症しやすくなるため注意が必要です。
4.口をポカンと開けている人
口腔内は粘膜で覆われ、通常は唾液によって潤っているため細菌の付着を防いでいます。しかし、口が常に開いていると乾燥しやすくなり、白血球の機能が低下して歯周病菌が増加します。鼻づまりなどで慢性的に口呼吸をしている方も注意が必要です。
5.歯ぎしりをする人
歯ぎしりは歯や歯ぐきに大きな力を加えるため、歯周組織に負担がかかり歯周病を悪化させます。特に「歯を横にすり合わせるタイプ」の歯ぎしりが最も悪影響とされます。
・横にギシギシすり合わせる歯ぎしり
・食いしばり
・歯をカチカチ鳴らすタッピング
歯は縦方向には約100kgの力に耐えられますが、横からの力には弱く、ダメージを受けやすいのです。
6.歯並びが悪い人
歯並びそのものが歯周病の原因になるわけではありませんが、歯磨きがしづらくなることでプラークが残りやすくなります。プラークがやがて歯石となり、歯周病につながります。
また、加齢によって歯並びが悪化する「フレアリング」と呼ばれる現象も起こりやすく、50歳以降に歯間に隙間ができる人も増えます。これにより歯磨きが困難になり、歯周病のリスクが上がるため注意が必要です。
7.降圧剤・抗てんかん薬・免疫抑制剤などを服用している人
中でも歯周病に影響が大きいとされているのが「降圧剤」です。これらの薬を服用している人の口腔内では歯ぐきの腫れが見られることが多く、薬剤による副作用が歯周病の引き金になるケースが増えています。特に中高年で血圧が高くなり、降圧剤を常用するようになってから歯周病を発症する方も少なくありません。